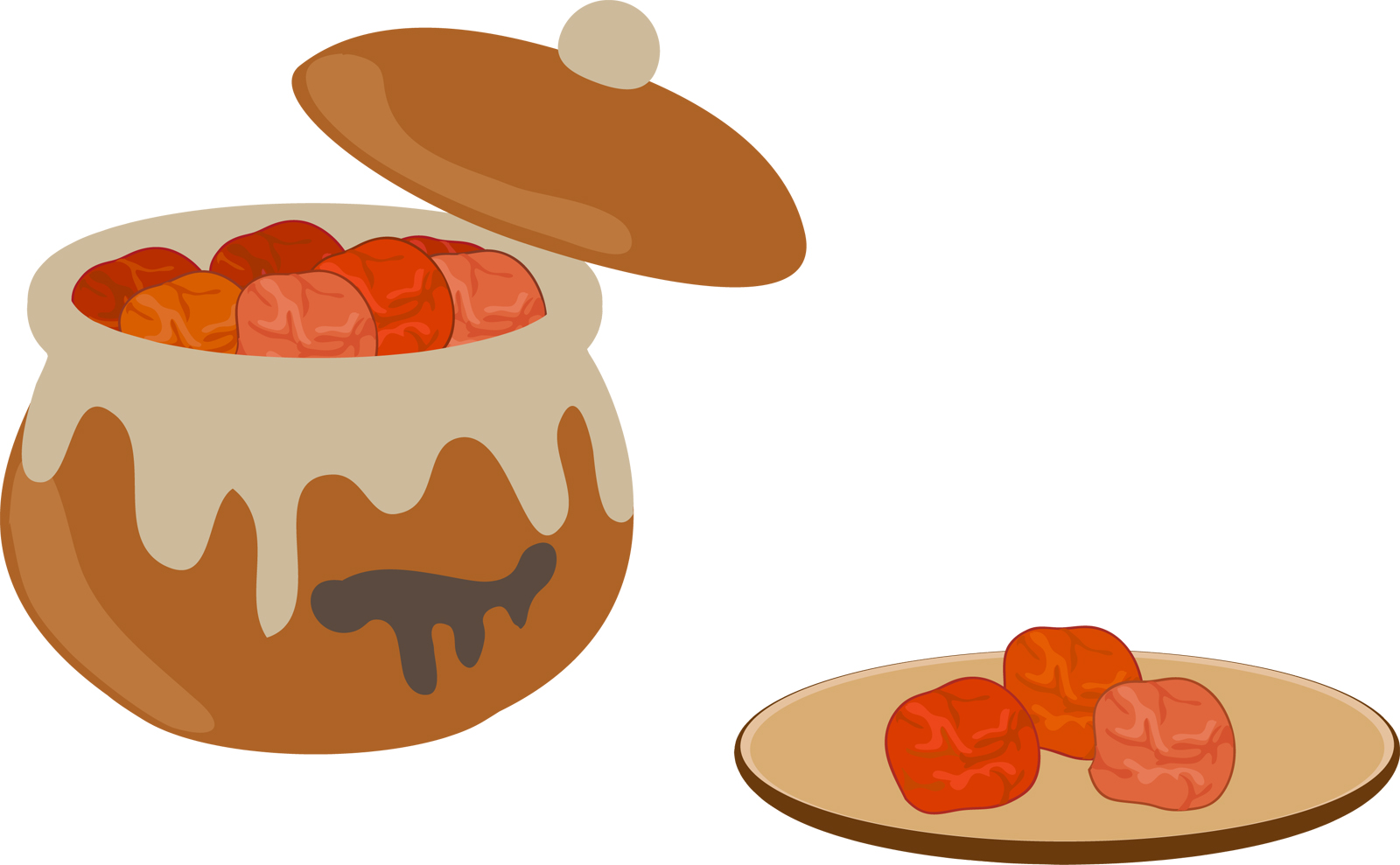◆ はじめに
夏になると必ず話題になる「土用の丑の日」。
「ウナギを食べる日」として知られていますが、
実はその背景には、古代中国の思想、江戸時代のマーケティング、地域ごとの風習などが複雑に絡み合った、奥深い歴史と文化があります。
この記事では、土用の丑の日の起源や変遷、現代との関わりまでを分かりやすく解説。
「なぜウナギなの?」「実は他にもいろいろ食べていた?」など、思わず人に話したくなる豆知識もたっぷりご紹介します。

2025年の土用の丑の日はは7月19日(土)と7月31日(木)だよ!
◆ 土用の丑の日って何?基本をおさらい
まず、「土用の丑の日」は**季節の変わり目である「土用」の期間中にやってくる“丑の日”**のこと。
夏だけでなく、春・秋・冬にも「土用」はあるんです。
とくに夏の土用(立秋前の約18日間)は、一年でもっとも体調を崩しやすい時期。
古来より、この時期は『養生の季節』とされていました。
十二支の「丑」は“育ち始めるけどまだ伸びない”という意味があり、まさに次の季節に向けた準備期間でもあるのです。
◆ 「ウナギを食べる」って誰が決めたの?
▶ 起源は古代中国の五行思想
「土用」は中国の陰陽五行説からきており、季節の変わり目は“土”の力が強くなると考えられていました。
日本に伝わると、民間信仰や健康観と融合し、「この時期は特に体をいたわるべき」という考え方が広まりました。
▶ 奈良時代にはすでに「夏バテにウナギ」
なんと『万葉集』には、ウナギを夏の体力回復にすすめる歌が残されています。
つまり、「土用にウナギ」は1300年以上前からあった知恵なのです!
▶ 江戸時代の仕掛け人、平賀源内!?
一番有名なのは「平賀源内がウナギ屋の売上対策として『本日 土用丑の日』の張り紙を提案した」という説。
しかしこれは、記録上やや疑わしい部分もあり、
源内が文化の普及に一役買ったというのが実際に近いと考えられています。
他にも、医師と組んで“夏でも食あたりしない食材”としてウナギを売り込んだという商人の戦略もあったとか。
いずれにせよ、健康と商売が手を取り合って発展してきたのが「土用の丑」のユニークな一面です。
◆ 地域ごとに違う「丑の日のごちそう」
▶ 「う」のつく食べ物は縁起物
ウナギだけじゃない! 実は「う」のつく食べ物ならOKというのが本来の考え方。
- うどん
- 梅干し
- うり(きゅうり、すいかなど)
- 馬肉、牛肉
いずれも夏の体を労わる栄養満点の食材ばかりです。
▶ 土用餅・土用しじみ・土用卵
地域によってはこんな習慣もあります:
- 土用餅(小豆あんで邪気払い)
- 土用卵(夏に産まれる卵は特に滋養あり)
- 土用しじみ(“土用しじみは腹薬”と言われるほど)
土用の食文化は、地域性がとても豊か。その土地に合った食材と知恵が代々受け継がれているんですね。

◆ 食べるだけじゃない!?丑の日の風習いろいろ
- 丑湯(うしゆ):薬草を入れたお風呂で夏の疲れを癒す
- きゅうり加持:願いを書いたキュウリを祈祷し、厄を封じ込めて川に流す
- 虫干し:書物や衣類を干して湿気を払う暮らしの知恵
どれも、「夏を元気に乗り切るための伝統的なセルフケア」と言えるでしょう。
◆ 現代における意義と課題
▶ ウナギの資源問題
実はニホンウナギは絶滅危惧種。
土用の時期は需要が集中し、資源保護とのバランスが大きな課題となっています。
・完全養殖の研究
・代替食材の提案(ナスや豆腐の蒲焼きなど)
・「う」のつく別の食材で文化を継承する工夫
“文化を守る=ウナギを大量消費する”ではない。
新しいスタイルの「土用の丑」が模索されている時代です。
▶ 食の多様化とグローバル化
近年では、ヴィーガン、アレルギー対応などのニーズも増加中。
また、海外でも土用の丑の日を紹介する日本食レストランが増え、日本文化の発信にも一役買っています。
**本質は「体をいたわる日」**であることを意識すれば、
どんなスタイルでもこの文化は未来へとつながっていくはずです。
◆ まとめ:ウナギを超えて広がる、日本の夏の知恵
「土用の丑の日=ウナギを食べる日」と思われがちですが、
本来は季節の節目に心と体を整えるための日。
そこには、先人たちの健康への知恵、自然との調和、食文化の多様性がぎゅっと詰まっています。
これからは、
✅ 体をいたわる一日としての「丑の日」
✅ ウナギ以外の楽しみ方も選べる自由さ
✅ 地域や家庭ごとの文化を大切にする視点
そんなふうに、あなたらしい「土用の丑の日」を過ごしてみてはいかがでしょうか。